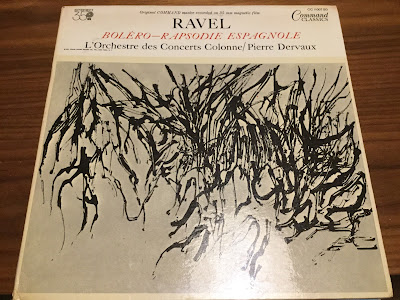この本は、かつて読んでかなり影響を与えられた。最近、クロスビーの『ヨーロッパの帝国主義』を読んで、今一度読み直そうと思う。
第一章 ポルトガルの「海の帝国」とアジアの海
1498年にモザンビークにヴァスコ・ダ・ガマ到着。その時のモザンビークでアラビア語が共通語として話されていたことに驚き。アラビア商人がすでに八世紀ごろには行き来していたらしい。インド洋海域では、ムスリム商人以外にも、グラジャート地方のヒンドゥー系、ジャイナ系、ユダヤ系、アルメニア正教系などの商人が交易活動をしていた。
沿岸の王国は「収入の多くを商人が持ち出す商品に課す関税に頼っており、遠来の商人にいかに有利な交易の場を提供するかにその浮沈がかかっていた。逆に、内陸部に拠点を置く政治権力は、港町とそこでの貿易を、収入源ついてそれほど重要視していなかった。多額の軍事遠征費を支出して港町を征服するよりも、そこで自由に貿易を行わせ。商品が内陸の王国の領内に入ったところで関税をかければそれで十分だと考えられていたのである。」39 カリカットのような港町では、いかに安全で公正な町であるかが重要であった。
カリカットの王に謁見の際、ヒンドゥー教徒や寺院をキリスト教と勘違いしたという。面白いのは、ガマがカリカットでの物価の安さ、富の豊かさに驚いているところ。当時のポルトガルとカリカットとのギャップ。この航海に約二年を費やしていた。しかし、彼がもたらしたものは大きく、それまで香辛料の交易を牛耳っていたヴェネツィアを苦境に追いやる転機となった。
カブラルの航海の失敗の後、再度ガマはインド洋に向かう。その際大規模な船隊を組み、大量の大砲を積む。まず東アフリカのキルワを制し、のちカリカットを武力で抑える。イスラム教徒は容赦なく殺されたという。ガマは当時の十字軍精神をもっていたという。ガマの航海から1510年まで(アフォンソ・デ・アルブケルケ治世)にインド洋西岸はポルトガルの支配を受け入れていった。時に武力衝突があっても、オランダ、イギリスの登場までポルトガル優勢となっていた。ただし、ポルトガルにとって香辛料が目的で、他のものを独占的に取引していたわけではない。その他の品は従来通り多種多様な商人が貿易を行っていた。
ポルトガルのこの事業は、王の名前でやっていたが、実際は事業に相当の金が必要でフランドルの金融業者からの借り入れでまかない、時代が下ると貴族に渡されていった。驚くべきことに長崎ーゴアの間の貿易額が突出していること。
カルタスの発行によってポルトガルは船を往来の管理をしていた。そこから積載された荷物に税をかけて収益をあげていた。このカルタスの制度はのちのイギリス東インド会社にも引き継がれる。
まさにこの時期ムガル帝国のアクバルが勢力をの場している時期だったが、ポルトガルは「海の帝国」でムガル帝国は「陸の帝国」ということで、守備範囲が異なっていたため利害が発生せず、衝突もなかった。「ムガル帝国の支配下にあったインド各地の商人たちが、ポルトガル人の圧力を受けて海上貿易で苦労している以上、肯定派彼らに対して援助を与えるべきと私たちは考える。だが、この意見は、近代的、あるいは東アジア的な国家や政治権力者の姿を前提としている。ピアソンという学者の研究によると、西北インドに会ったグラジャート王国では、王は彼の領域内に住む人々の集団と強い政治的な関係をもたず、商人たちの行っている事業に関心がなかった。したがって、巨大な金額を使って軍を動かし彼らを保護せねばならないとも考えなかったという。これは当時のインド洋沿岸の政治権力について、ある程度一般化できる原則である。ムガル帝国は、商人が定められた税額さえ支払えば、彼らが行っている商行為や他者が彼らに及ぼす影響などには無頓着だったのである」65-66
1511年、ポルトガルはマラッカを支配し、さらなる東アジアへと視野を広げていった。
ポルトガルの事業は、すぐに傾き始める。ヴェネツィア経由の交易ルートが多数開発され、ポルトガルの優位が保てなくなり、結局ポルトガルとヴェネツィアでの価格差がなくなっていき利益を求められなくなっていった。そして16世紀にオランダの登場となる。
第二章 東インド会社の誕生
スペインの無敵艦隊をイギリスが撃退したのが1592年。「レヴァント会社」という地中海東岸地域の貿易を個なっていた会社がオランダの隆盛をみて、一回の航海で必要な資金を出資者から募り、航海が終わった後元本と利益を出資者に戻すという方式をとる。まだ株式の登場ではない。この出資者は、イギリス人とは限らず、多国籍な面もあった。1601年にイギリス東インド会社(East India Company)が設立される。
東インド会社は、エリザベス一世からの特許上を得ているが、民間の会社であり、またアジア地域の制服を目指したものではなく、貿易会社にすぎない。結果的にアジアの海を制覇するが、当初はその気はまったくなかったようだ。
1602年、オランダ東インド会社(Vereigde Oostindische Comoagnie)が、複数のからなる連合会社として設立される。オランダの場合は要塞の建築、提督の任命、支配権など、准国家てきな存在であった。1619年、バンテン王国の港ジャカルタに拠点を作る。バタヴィアと名付けられる。この時バタヴィアには71名の日本人がおり、東インド会社の傭兵をしていたという。
ルン島事件、バンダ虐殺。
17世紀末ごろにはオランダは東南アジア海域から他のヨーロッパ諸国の商人を排除することに成功。なぜに日本の長崎、平戸では要塞のようなものを作らなかったのか。
インドやペルシアはヨーロッパの会社に有利な条件を与えている。なぜか。寛大さ、気前のよさ。歓待の習慣、またはイギリスやオランダの武力の活用、などが考えられるが決定的ではない。
バタヴィアとオランダ本国との往復は一年半を要する。そのため多くの決定が総督によって行われた。権力の集中が見られる。すでに「国」のような感じとなっっている。当時、有限責任制や株式の売買などが行われるようになった。
第三章 東アジア海域の秩序と日本
後期倭寇の出現と北方モンゴル系の侵入に苦しみ(北虜南倭)、1550年台も明帝国が危機に瀕する、という説明の前提には、陸の帝国である明は海も支配しているという前提が組み込まれている。なるほど。この説明を敷衍し、サファヴィー朝やムガル帝国は、ポルトガル人に苦しんだのか? そんなことはない。当時の港はイラン系、インド系、アルメニア系など多くの人たちが貿易をしていた。しかし、東アジアの文脈では、陸の国家が海上貿易を規制、管理するものとみられている。
朝貢貿易制度をずっと維持してきた中国の歴代王朝。民間レベルでも貿易は盛んだった。しかし明は朝貢貿易のみを許した。渡航禁止制度を儲けてもいた。明という国家の特徴。なぜこのような措置を取ったのかは謎。
そしてこの朝貢には多くの国々が応じている。朝貢制度では、国と人が一致させることで管理していた。いわゆるパスポートのようなものだ。
当時、日本産品は売れず、むしろ日本は中国の品物をほしがった。日本では大量に銀を生産し中国へ輸出していた。
ポルトガル人が最初に中国にきたのは1513年。朝貢貿易をやろうとしたが失敗。悪いことにインド洋海域で行っていたような武力で用いて貿易を行おうとした。しかし、ポルトガル人は陸の帝国である明は、陸と同時に海も支配していた。そのため要塞を築いていたタマオ島(屯門島、香港の近くの半島のようなところ)に攻撃をしかけられ、結果敗退。1542年、鉄砲日本伝来。
五島列島から平戸まで、密貿易を行っていた中国人やポルトガル人がいたようだ。ポルトガルはなんとかマカオを獲得。東アジア貿易の拠点を作る。ここで重要なのは、明帝国はポルトガルに遺留を認めただけで、インド洋のように割譲または支配されていたわけではない。マカオが植民地になるのはアヘン戦争後のイギリス領からとなる。マカオの建設で、ポルトガルは日本との貿易が簡単になる。重要なのはポルトガルはリスボンからの荷物を売っていたのではない。中国と日本の間にはいって中国の商品をさばいていた。
東インドにおいてポルトガルが布教することは、領土獲得とセットとなっている。キリスト教の布教と貿易も切っても切れない関係で、当時、多くの大名が回収した理由の一端がここにある。イエズス会は長崎を要塞化しようとしていたが、当時の日本の支配者はイエズス会の目的が純粋な貿易と布教にだけあるのではないことがわかっていたようだ。
秀吉の天下統一と東アジア、ひいては世界史的な見方。
中世まで日本は群雄割拠していたが、秀吉が16世紀後半に統一を果たす。名古屋城、伏見城、聚楽第等の大規模な建設、そして朝鮮出兵。これらは明帝国を中心とする東アジア秩序への朝鮮でもあった。この朝鮮出兵は大きな意味をもち、これ以降豊臣政権、徳川政権ともに明そして清との外交関係をもつことなかった。ここから徳川政権の海外貿易における独自の道があらわれてくる。それは鎖国とキリシタン禁止である。
日本と明との間の貿易は大内氏の滅亡後、明の海禁政策により華人、日本人ともに貿易ができなくなっていた。そこにポルトガル人が仲介をするようになる。ただし、東南アジアでは日本と華人との間で、取引はあった。徳川の朱印制度はと東南アジア諸国に朱印状を持つ船の安全を求め、そして船は必ず長崎の港を使うことが決められていた。これは徳川の貿易の管理だが、安定的な貿易のため朱印状は、華人、ヨーロッパ人にも渡されていた。これはまさに明の秩序からの離脱を意味しており、さらに言えば東アジアにおける権力の範囲が陸だけでなく海をも含んでいたことを証明している。これが鎖国政策の意味であり、「海上貿易」を遺漏なく管理することこそ、徳川政権が権威ある政権として認められるための道だった。」136
つまりポルトガルがなぜ長崎を拠点に要塞を築くことができなかったか、ひいてはインド洋の港のように武力的な介入ができなかったかの一つの答えとなる。なぜ秀吉、徳川がキリスト教布教を嫌がったのか、それは布教が領土問題と重なっていたからとなる。キリスト教を禁止したのは、日本だけではなく清、朝鮮、ベトナムも禁止にした。これは東アジア特有の現象と言ってもいい。
オランダ東インド会社は、当初マカオを武力で背圧しようとしたが失敗し、台湾の台南でゼーランディア城という要塞を築く。オランダは平戸で商売を許すが、ここはオランダにとって軍事拠点であり、ポルトガル船への攻撃に適していた。驚くべきことにオランダ東インド会社の収益のうち平戸での割合は7割以上だったようだ。そりゃ、事を荒立てずに徳川政権に従ったほうがよい。オランダは東アジアにおいては、インド洋や東南アジアのような拠点や要塞をつくれずじまいだった。
第四章 ダイナミックな移動の時代
18世紀に「華人の時代」と呼ばれるように、多くの華人が東南アジアの海で活躍し、東南アジアで移住するものや政治権力を握るものも現れる。まアユタヤ朝ナライ王のもとにはペルシア人、フランス人、ギリシア人などがおり、当時は国民国家的な枠組みがないことが伺われる。これは日本と対照的なこと。オランダ東インド会社は、鄭成功との戦いに敗れた1662年以降、台湾を放棄しバダヴィアで中国との貿易を継続した。華人は砂糖を製造し、オランダ東インド会社はそれを買い西アジアや日本に売っていた。
イラン系はムガル帝国やアユタヤ朝にも進出していた。アユタヤ朝ではとくに商業に従事し、長崎との貿易もしていた。そのため1672年にモウル通詞の役職ができる。またインド系は西に移動し、サファヴィー朝ペルシアに移住するものなどが多く出た。
アルメニア系の人々は、イスファハーンに特別居住区が設定されペルシア産の絹織物の貿易に従事させた。この街をジョルファーにちなんで、新序ルファーとよび、彼等は金融業としも活躍、カトマンズやラサにまで活動は及んでいた。
重要なことは、アジア系とヨーロッパ系はインド洋やアジア海で入り乱れながら交易をしていた。インド洋にある王権は商人を歓迎しており、その商人が華人かヨーロッパ系などは問わなかった。徳川政権は逆に「内」と「外」を区別していた。
イギリス東インド会社の場合、船は所有しておらず借りていた。船乗りも船主側が雇うかたちになり、イギリス東インド会社は貿易会社となる。
オランダ東インド会社の場合は貿易業だけでなく、造船業、海運業を含む複合型企業。
また、彼等の船はヨーロッパで必ずしも作られたものではなく、現地生産されている。
ヨーロッパからアジアまでおよそ8ヶ月かかる。これほど時間がかかるのに、よくもまあ港を制圧していったことよ。
オランダ東インド会社では、常に人手不足で外国から多くを雇っていた。また現地人も多く雇っていた。
第五章
長崎出島の場合。
オランダ東インド会社のみが交易を許されており、出島は天領であった。彼等はあくまでも「店子」の立場であった。外国人が日本で不動産を取得することは許されていなかった。日本の商人がオランダ東インド会社に建物を用意しているかたち。しかも家賃がかなり高かったようだ。華人の場合は163年まで自由に長崎市内を往来できたが、長崎南東の唐人屋敷の区画のみとなり、時には帰化するものがでてきて、帰化したものの中から中国語を通訳する「唐通詞」が生まれる。つまり、当時すでに華人やオランダ人をはっきりと「外国人」として区別していた。
出島が持つ、他地域のヨーロッパ商館との違いは、武力や兵士を持ち込めなかったこと。すべて幕府側が統制するという、世界で唯一の体制を整えていた。
マドラス聖ジョージ要塞の場合
当時のマドラスの豪族ナーヤカから特権を、イギリス東インド会社はもらう。1 好きなところに要塞を築ける、2 建設費はナーヤカが負担し、入城後返還、3 マドラス港の関税は折半、4 それ以外のナーヤカの領地での貿易の観世は免除、5 貨幣の鋳造の許可。これらの条件は武力で勝ち取ったのではなく、ナーヤカ側から自ら条件をだしたもの。これは大村純忠がイエズス会に長崎の寄進を思い浮かべれば、日本でも起こっていたこと。貿易での収益が重要であり、土地にたいする考えが、国民国家とは違う。日本では徳川の時代に大村純忠のようなことはできなくなるが。イギリス東インド会社の商館周りにはブラックタウンという職人や商人が移住してきた人の区画ができる。 中心地をホワイトタウンという。またヒンドゥー教やアルメニア系、ムスリムなどが混在し、宗教的自由が保証されていた。
しかも面白いことに、裁判も当初は現地人かヨーロッパ人かを裁くのにナーヤカとの交渉があったりしたようだが、17世紀半ば以降はイギリス東インド会社が裁判権をもつようになる。しかし、会社側からすれば余計な業務であり、やりたくなかったようだ。あくまで商業の従事したかったようんだ。そして複雑な案件をロンドンに問い合わせるなどがあり、現地での貿易と統治を分割するようになり、総督という職が創設される。
バンダレ・アッバースの場合
マドラス同様エスニシティ、宗教のるつぼ。サファヴィー朝は貿易を管理することはなく、シャーバンダルという職を設けて、徴税をするのみだった。そして複数の東インド会社が互いに競争していたばしょであった。
当時、交渉がうまくいかない場合、東インド会社は武力をもちいることを厭わなかった。にもかかわらず、出島では武力をつかわず、政権側の意向に従っていた。イギリス東インド会社は、ホルムズ制服に貢献したため、アッバース一世から、関税を半額という特権を得ていたが、アッバース一世の没後、政府側から破棄される。会社側は「条約」と見なしていたが、帝国側は「恩恵」と考えていた。
第六章
混血児について。ある時はマカオやじゃがらた(バタヴィア)に追放される。
オランダ東インド会社にとって、混血児は慢性的な人手不足の中で貴重な財産でもあった。
おてんばコルネリアについて。『おてんばコルネリアの闘いーー十七世紀バダヴィアの日蘭混血女性の生涯』(平凡社)が紹介されている。「おてんば」がオランダ語のontembaar手に負えないが由来とは。興味深いのは、初期徳川政権は混血児に対して厳しい態度を取っていたがオランダでは混血であることは問題とされていないようだったこと。
遊女との間の混血児の場合、1715年には、混血児を父親が帰帆する際などに連れて帰ることを禁止にしたりしていた。このあたりで混血児を「内」と認識していたようだ。ただし、遊女の子供ということで春やコルネリアのように財産を築いたという人はいないようだ。このあたり悲しい。おそらくは「紅毛人」というように差別があったことも確かで、妊娠した遊女は多くは堕胎したという。遊女の格も、オランダ人相手の遊女は一番低いとされていたようだ。
イェールについての記述。東インド会社の総督にもかかわらず私貿易で巨万の富を得て、大学などをたてたりする。
ダニエル・シャルダンについての記述。東インド会社の社員ではなく、自由商人としてマドラスへ。驚きがアウラングゼーブがゴールコンダ王国を滅ぼした直後ぐらいに、ダイヤモンドを探しに現地に赴いていたこと。当時、ゴールコンダ王国からイギリス東インド会社は多くの恩恵を得ていたが、ムガル帝国に取って代わられることで交易の優位を引き続きえるための旅でもあったという。
オランダ、イギリスのホルムズでの立ち位置についても書かれている。
第七章
明治に紅茶やコーヒーを「先進性」として日本は捉えたが、ヨーロッパにおいてもこれらの文化が成立したのは、18世紀末から19世紀になってから。
東インド会社が果たした世界を結ぶネットワーク。香料はヨーロッパで非常に愛されたりした。ここで疑問なのが、日本では肉料理を食べなかったから、香料を¥に興味を持たなかったと書いてあるが、どうなのか。胡椒や白檀、他に多くの香料が日本に入ってきていいではないか。
よく香辛料を保存のためと言われているが、どうも怪しいとのこと。1 保存剤であれば塩、酢、植物油で十分。2 肉は現在よりも新鮮な状態で食されていた。3 腐肉、保存肉は貧乏人の食べ物。4塩漬け肉は一般的にマスタードで食べられていた。
なぜヨーロッパで香辛料が流行ったのか。まず、医薬品と見られていた。漢方みたいん感じだ。(『食の歴史』J・L・フランドル著 藤原書店)
18世紀半ば頃には、香辛料の売上の割合は低くなっているが、それはコーヒーや紅茶、繊維などの商品の売上があがっているからだ。事実として、香辛料の売上はのびなかった。おそらくそれはヨーロッパ社会で定着したものとなったらと思われる。
ヨーロッパでの茶の受容について。16世紀にマカオから仕入れた可能性がある。確証ないが。フランスでは1635年頃に持ち込まれている。18世紀に入り、数字として輸入統計がはっきりしてくる。コーヒーは茶よりも伸びが悪かったようだ。イギリスでは1640年ごろに伝わり、1650年代にコーヒーハウスが多く出店され、茶がだされるようになる。18世紀前半頃にようやく普及し始めた。ヨーロッパでは茶は高級品であったが、シャルダンはアジアでは非常に安価で売買されているという報告をしている。オランダでは日本式の所作を取り入れた熱すぎるお茶を大きな音をたててズルズルすすっていたりしていたようだ。さらに当初はヨーロッパでは緑茶であったが、1730年ごろに紅茶の消費が逆転する。理由は、水質だけが問題なのではなく、何かがあるはずだが、なんとも言えないところ。値段、収穫量などなど。イギリス、オランダの上流階級ではどうも緑茶が好まれていたようだし。
インド産綿織物がヨーロッパの社会を変える。従来の麻や絹、羊毛など業者は抗議したり、実力行使したりして、イギリスでは、死体を毛織物で包むことを法律化したりした。しかし、安価で優れた面はヨーロッパで浸透していった。日本でもまた同じ時期にインド産の織物、唐桟、奥嶋が流行る。
17世紀におけるアジアブーム。
第八章
フランスの東インド会社設立の遅れ。地理的条件によって、海への志向がうすかったよう。またコルベールが主導したことから伺えるように政府と一体的な存在だった。たしかに株式は公開されていたが、総会での議決権はないなど、イギリス、オランダとは異なる。フランスにてっとポンディシェリは、オランダ東インド会社のバダヴィアのようなところ。
当時アジアの海ではフランスをはじめ国旗を掲げたりしていた。それは武力の誇示でもあった。しかしヨーロッパ以外の船、または現地で艤装した船は国旗を掲げていなかった。国家のあり方が、ここでも違う。
アウラングゼーブの死後、ムガル帝国内は混乱する。陸の帝国であるムガル帝国にたいし、各東インド会社は闘いを挑むことはしなかった。あくまで貿易業務に集中しようとしてた。港を武力で制圧することはあってもムガル帝国本体にはけんかを売るべきではないと考えていた。ムガルの混乱は会社にとっても不都合だった。そこで会社の商館や居留地では軍事力を増強するようになる。たとえばシパーヒー(セポイ)。
あることがきっかけでインドの歴史が大きく変わってくるようだ。アルコットの太守(ナワーブ)がデカン高原でマラーター勢力との争いの末殺され、息子が反撃しようとした時、ポンディシェリの総督に財産と家族を匿ってくれるように要請。これ以降、友好関係を樹立。マラーター軍は撤退後、感謝の印としてナワーブはポンディシェリ近郊の村2つをフランスに譲り、ムガル帝国はフランス人を「太守」としてした。
カーナティック戦争について。1740年にオーストリア継承戦争が勃発したのと同時に、インドでフランス東インド会社とイギリス東インド会社のあいだ争いが起こる。ただし、国家間の戦争ではない。会社間の争いで、事実オランダ東インド会社は参加していない。オーストリア継承戦争ではオランダはイギリスとともにオーストリアを支援したにも関わらず。ポンディシェリ総督のデュプレスクは統一の制服、統一の訓練など採用し、アルコットの新ナワーブ軍を破る。大陸で初めてヨーロッパの軍隊がインドの王侯を破った闘い。ラ=ブルドネは戦艦を率いてマドラスを陥落させる。オーストリア継承戦争が終結し、マドラスは返還されたりするが、関係が激化していき戦闘が続く。1761年まで断続的続くこの戦争をカーナティック戦争と総称する。
貿易業務に専念したいフランス本国は、デュプレスクを本国にもどす。これによりインドでの軍事的優勢はなくなる。
ベンガルで、当時のナワーブは各国東インド会社を快く思っていなかった。特にイギリス東インド会社は攻撃をうける。ナワーブは味方の裏切りにあい、敗北。イギリス東インド会社に新ナワーブは賠償金を支払う。この戦いを境にイギリス東インド会社は、貿易会社の枠を超えて「領主」の地位となる。事実、ナワーブからジャーギルという地位を得る。
ここで疑問が残る。なぜイギリス東インド会社はプラッシーの戦いだけでベンガルの領主になれたのか。問題なのは、武力で勝ち取ったのではなく、恩賞としてもらったのだ。
当初プラッシーの戦いで助けてくれた東インド会社に恩賞を与えるものだったが、すでにこの時には時代は変わっていた。イギリスと近代国家となっており、インドでの武力の差はナワーブとは差がついていた。恩賞だったものが、いつのまにか性格を異にするものとなっていた。単なる貿易会社が、まさに領主となっていた。
第九章
イギリス東インド会社はベンガルでディワーニーという財務長官の職を得る。単なる商事会社が「統治」ができるわけもなく、税の徴収もできるわけもなく、軍事費などが嵩み、財政的に困窮するようになる。さらにアメリカでのイギリス東インド会社を経由する茶の不買などなど。そこで政府が会社の株式を買い、政府のバックアップのものと、ベンガル、マドラス、ボンベイと別れていたものをベンガル総督が全てを総括し行政の見直しをおこなった。初代総督はウォレン・ヘイスティング。
再三の財政危機、個人の巨大な蓄財、現地の統治能力などが、本国で疑問に上がり、インド法が1784年にできあがる。これにより実質的にイギリス東インド会社は政府の監督下に入り、これまでのような自由な地位を失うことになる。アダム・スミスの批判があるように、独占貿易の時代の終焉となる。
フランス東インド会社は七年戦争やイギリスへの賠償金などで財政危機に成り1769年に解散となる。イギリスより先に自由貿易を行うようになる。
オランダ東インド会社は、複合的な理由により1795年廃止。英蘭戦争が原因と言われているが、汚職、経営陣の無能、高い配当率、本国とバダヴィアの不和などなどが複合的に重なった結果。
1800年頃までにインドでは、藩王国というものができる。イギリス東インド会社の軍事的庇護を受け、商業的な権益を渡すといったもの。さらにもともと西方イラン系の北インドを指していた言葉「ヒンドゥー」が宗教の概念と結び付けられ、あたかもひとつの、キリスト教やイスラム教のようなまとまった宗教集団であるかのように、インド亜大陸の信仰をまとめて、「ヒンドゥー」と呼ぶようになる。そしていつのまにかインドの人々は自らを「ヒンドゥー教徒」とよぶようになる。
ペルシアはインドと異なる道をたどる。政治の混乱、人口の少なさ、交通網の不安定さなどがあり、バンダレ・アッバースやイスファハーンの商館を相次いでオランダ、イギリス、フランスもたたむ。イラン高原ではカージャール朝が成立する。トルコ、インドなどに挟まれたこの地域は植民地にならずにすむ。
東アジアでは、インド海域とは異なる状況だった。清朝はカントン・システムを採用し、短期間だけのヨーロッパ人の滞在以外はマカオに居住することを強制していた。日本も貿易を限定していた。ただ、ヨーロッパ、アメリカ共に清との貿易量は増加していくが、主導権は清朝側にあり、たとえばイギリスと北京に大使館を起きたいと乾隆帝に頼んだが拒絶されるなど、海の支配権を手に入れるのにはまだまだ時間がかかっていた。
日本においては段階的に「鎖国」制度が強化されていき、新井白石によって正徳新例がさだめられ、オランダ、清ともに貿易量が限定されるようになる。海外貿易依存度が小さいため、日本国内での自給自足ができあがる。生糸、木綿、砂糖、磁器など、自ら作れる体制をなっていった。これはなかなか面白い現象。この環境は明治まで続くし、経済のあり方として、明治以降の日本社会を考える上でも重要かもしれない。
おわりに
北西ヨーロッパでは気候が冷涼なこともあり食料生産性が低く、また金属などの産出はアジアの現地でもでき、北西ヨーロッパの工芸品や織物はアジアでは需要があまりなかった。インドの面は高品質な上大量生産により安価だった。このようなハンディキャップを克服できたのはアメリカ大陸の存在だった。アジアの物産を交換する際に使用したのが、南北アメリカで産出した銀だった。日本の銀も一時期使用されていたが、それは1670年頃まで。アメリカ大陸発見は、ヨーロッパの近代化の基盤を生み出していた。
「国籍」という概念自体、中世ヨーロッパには存在せず、ゆるやかなヒエラルキーで形成された社会だった。アジア地域でも、ムガル帝国やサファヴィー朝などがあったが、そこに住む人々をムガル人やサファヴィー人とはいわず、複雑な集団の、多元的世界が広がっていた。東インド会社が好待遇を受けたのも、集団として現地の政権に何かしらの貢献をしたからであり期待されたからである。
イスラーム教は地縁や職業、エスニシティを超越する宗教として、統治する上での理念を権力者にもたらしていた。アジアの港町でイスラーム教に改宗したのは、権力者からだった。
日本では、世界の動きとは逆に貿易を縮小していった。なぜそれが可能だったのか。
*************************
多くの示唆を与えてくれる。日本の「鎖国」は世界的にみてどんな位置にあったのか。国家とは何か。近現代史の前史としてある、アジアの海がどのような状況であったのか。インドの植民地化がなぜなされてしまったのか。
歴史は非常に複合的な積み重ねで、単線ではないことがわかる。特にインドの植民地化については、よくわからないことだらけだ。なぜ巨大なインドがイギリスの植民地になってしまったのか。「統治する」とは何なのか。簡単に統治するといっても、ことは複雑で、現代人的な考えをすれば、被支配民は立ち上がってイギリスに立ち向かわなかったのかなど考えられるが、それは国にアイデンティティがあってこその行動なのだろう。誰が統治しようとかまわないというのが事実で、現代では宗教、エスニシティが統治の基本となっているため、なかなか当時の現状を理解できないところもある。徳川政権での自給自足体制や、国家観なんかはその後の近代化のことを考える上で重要な事だろう。