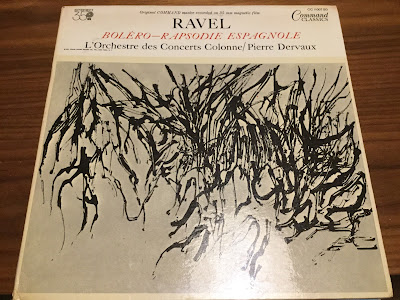第一章 仏教は正しく生きるための道ではない。労働や生殖を否定している。世の流れに逆らう生き方となる。ブッダの目標は解脱・涅槃に至ること。
第二章 心が汚れていること「有漏(うろ)」。煩悩がなくたって汚れない状態「無漏(むろ)」。盲目的な慣習的行為を永久的に差し止めることが、悟りへの道となる。
mindfullnessは、一つ一つの行為に意識を行き渡らせ、無意識な行為を防止しようとする「気づき(sati)の実践。
諸行、つまりあらゆる現象は無常である。全ての現象が原因(条件)によって成立している。そしてかならず消滅する。これが縁起。
「苦」は、英訳でunsatisfactoriness。つまり常に満ち足りていない状態。
「無我」は「己の所有物ではなく、己自身でもなく、己の本体でもない」
すなわち諸行は無常であり、本体は存在しない。言葉を変えれば、本質なるものは存在しない。存在論の否定となる。故に「無我」なのである。
業とは、「行為」「作用」、さらにはその結果もたらされる働きのこと。
衆生が煩悩と業のはらたきによって、苦なる輪廻的な生存状態に陥る次第のことを、「惑業苦(わくごっく)という。
四諦は、苦諦・集諦・滅諦・動諦をいう。
生は苦であり(苦諦)、その原因は渇愛であうり(集諦)、それを滅尽させることであり(滅諦)、その方法が八正道である(動諦)。
第三章 仏教において出家するとは、俗世間からの脱出を意味する。俗世間の善悪を否定しないが、それを捨てること、そこから解放されていることが、解脱となる。つまり、「優れた人物」となるための道を説いているのが仏教ではない。たとえ阿羅漢になっても実社会では役立たずであるかもしれない。世俗の善悪や判断基準から離脱することが重要となる。一種のルサンチマンか? 故に仏教は世直しとは無縁となる。
第四章 「無我」と言う時、否定されているのは、「実体我」
「常一主宰」である。これは、つまり全て自らの身体をコントロールできるという幻想。
ブッダは非存在を主張しない。沈黙する。無記。
時間とは何か、空間は有限か無限か。霊魂とは何か。如来は存在するか。などの形而上学的な問にたいして無記をとおす。
「「私」と呼ばれる認知の場のどこかに、常住で単一で主宰する権能をもった実体我が存在していると考え、それに執着して苦の原因を作ることがあってはならない。だからゴーダマ・ブッダは、その認知の場を形成する諸要素の一つ一つ、例えば五蘊を列挙して、それが全て「我ではない」ことを指摘した。」91
輪廻とは幼虫から蛹になり、蛾となるようなもの。幼虫と蛾は同一といえるが、異なるとも言える。
「無我だからこそ輪廻する」。移りゆく姿は、縁起によって引き起こされる。それは連続していていること。現象が生起し、継起し、滅尽する。そして新たに生起し・・・といったプロセスが輪廻となる。何が輪廻するかという問いはナンセンスとなる。
もし輪廻ががなければ、単なるニヒリズムに陥る。修行する意味がなくなる。輪廻を前提としない修行は、無意味だ。なぜなら死ねば、すべてが終わると考えられるから。解脱への最短への道が自殺ということになる。
第五章 世界は認知によって形成される。この世の苦や輪廻から解放されるということは、この世界の外にでることではなく、「想と意とを伴って、この一尋の身体のいおいて」実現されるものである。
「世界の終わり」とは、認知を終わらせることではなく、「戯論寂滅」である。119
イメージ、物語は苦である。これから解放されること、あいのままの現象をみること、それが「世界の終わり」へと導く。
自らの煩悩に気づくこと、世界の現象に意識を行き渡らせることで、それを物語の発展させたり、執着することもなくなる。
第六章 解脱・涅槃は曖昧で抽象的なものではなく、具体的かつ、明確に達成し得るものであると、ブッダは説いている。
煩悩の流れに気づくことは重要だが、それだけでは足りない。その流れを根絶することも必要とされる。「根絶できた」という宣言をするには、なにかしらの経験が必要となる。それが「智慧」である。
「「悟り」の内容は「三明」であると言われる。「衆生死生智」「漏尽智」「宿住随念智」。
如実知見は概念的思考や日常意識を、禅定の集中力によって越えたところに認知されるものだから、そこで生じる智慧というのは、思考の結果だということはあり得ない。」139
解脱は理性や意思の操作外であること。
「生起が諸行であり、不生が涅槃である」
「五蘊の滅尽は常である涅槃である」
「五蘊の滅尽は楽である涅槃である」
全てが無常なのではない。涅槃は常である。涅槃は原因や条件によって形成されたものではないので「無為」といわれ、無常ではない、常となる。
「現実存在」する苦から目を背け、それを概念操作で「なかったこと」にしてしまうのではまったくなくて、苦の現実をありのままに知見し、その原因である渇愛を残りなく滅尽させることで、それを正面から乗り越えるためには、不正であり無為である涅槃の覚知を必要とする理由は十分にあること、そして、ゴーダマ・ブッダ自身もその領域の存在について語っていた」156
「涅槃とは一つの経験です。」159
第七章 慈悲について。「慈・悲・喜・捨」の4セットで慈悲。捨は、心の動きを全て平等に観察して、それに左右されない平静さのことをいう。なので悟ってから出ないと本当の慈悲はもたらされない。単なる利他的行動が慈悲ではない。それは「不仁」の境地。これは、非常のこと。
悟った後、ブッダは衆生に語ることをしなかったが、あわれみの心をもって、理解できるものには「不死の門」を開くことにした。
では、悟った者の中に慈悲が存在するとはどういう状態か。利他行動は物語なかの行動である。智慧と慈悲の併存。これは矛盾するものが併存していると考えられるが、そう思考してしまうこと自体が、物語のなかで考えていることになっている。
無意味と口にすることが、新たなる意味を生成している。これは人間のものつ根源的な欲望なのかもしれない。
「一部の利他行の実践へと踏み出すのも、もちろん「遊び」ということになる。彼らは「必要」だからそれをするわけはないし、「意味がある」あらそれをするわけでもない。「ただ助ける」ことにするのである」176
第八章 略。
以上。
テーラワーダ仏教の骨格がわかる。俗世間と出世間のかかわりなど、私なんかは大乗仏教に親しんでいたので、テーラワーダ仏教が結構冷淡に見えなくもなかった。
ただ、悟りとは何かが非常に概念的に理解できるものだというのが面白い。あと一歩はやはり智慧が必要だが。
第七章での「遊び」の解釈は面白い。悟ったからと言って優しい人間になるとか、そういうのが悟りでも涅槃でもない、それは自己の究極的な境地で、それに達した人にとって、世界の見え方が平静にみえ平等にみえる。そこには利他的な行動を起こすことへの欲望もなく、単なる自由意志として存在する。極言すれば、「遊び」だと。